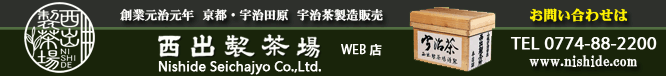 |
| TOP >> 会社概要・沿革 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
| 【会社概要】 |
|
|
|
| 事業所名 |
株式会社西出製茶場 |
| 住所 |
京都府綴喜郡宇治田原町
禅定寺東奥谷59番地 |
| 電話 |
0774-88-2200 |
| FAX |
0774-88-5289 |
| 代表取締役 |
西出 孝 |
| 店舗責任者 |
西出 淳子 |
| 事業内容 |
茶製造加工業
茶専門店様への卸売業
小売による直接販売 |
| 所属団体 |
全国茶商工業協同組合
京都府茶協同組合
京都府茶取引安定基金協会
等 |
|
 |
|
|
| 【西出製茶場の歩み】 |
|
|
| 元治年間 |
西出小十良による茶農家に始まる
|
| 明治時代 |
西出小重郎によって東京など消費地での茶の卸売りを始める
当時森本という場所に自園をもったため西出森本園の名で商売を行う。その後、西出製茶所を経て現在の西出製茶場となる。 |
| 昭和40年 |
茶専用冷蔵庫建設 |
| 昭和44年 |
京都府知事より創業100年を超える老舗に対する認定及び表彰を受ける |
|
その後総合仕上機・乾燥機・選別機・真空梱包機などの設備の近代化を進めながら現在に至る |
| 平成16年 |
関西茶業協議会より茶業功労者の表彰を受ける |
| 平成20年4月8日 |
社名を株式会社西出製茶場に変更 |
| 平成20年10月31日 |
店名の「西出製茶場」を商標登録 |
| 平成22年2月 |
当社の新事業である「京ふか冠茶」の開発が、経済産業省及び農林水産省より、農商工等連携促進法に基づく農商工等連携事業計画として認定を受けました。 |
| 平成22年3月 |
製品の衛生管理のため、CCDカメラを搭載した茶葉専用異物除去装置を導入。 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
当時をしのばせる商品札
|
|
|
|
|
「京ふか冠茶」ロゴマーク
|
|
|
|
| 【品評会での主な受賞歴】 |
|
|
| 昭和62年 |
宇治茶品評会 煎茶竹の部・煎茶梅の部にて入賞 |
| 平成2年 |
宇治茶品評会 玉露松の部・煎茶竹の部・煎茶梅の部にて入賞 |
| 平成3年 |
宇治茶品評会 玉露松の部・玉露竹の部・煎茶松の部・煎茶竹の部にて入賞 |
| 平成4年 |
宇治茶品評会 玉露松の部・玉露梅の部にて入賞 |
| 平成5年 |
宇治茶品評会 玉露松の部・玉露竹の部・煎茶竹の部・煎茶梅の部にて入賞 |
| 平成6年 |
宇治茶品評会 煎茶松の部・煎茶梅の部にて入賞 |
| 平成19年 |
宇治茶品評会 玉露竹の部にて入賞 |
| 平成20年 |
宇治茶品評会 玉露竹の部にて入賞 |
| 平成22年 |
宇治茶品評会 玉露梅の部にて入賞 |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
◆代表者ご挨拶
|
|
|
|
私達は、京都宇治田原にて140年以上の長きにわたり宇治茶の栽培・製造に関わって参りました。そして宇治田原は、1738年に永谷宗圓翁が青製緑茶製法を発明して現在の緑茶の基礎を築いて以来、日本のリーフティーの発祥の地とされております。
宇治茶は、江戸(東京)の商人によって国中に伝えられ、その後、煎茶道の作法などを通じて日本の文化の一翼を担うまでに発展をとげました。その後、緑茶は広く一般に普及し、生活に深く浸透するに従い、生活用品として欠かせぬものとなりましたが、その半面、近頃では日本茶の嗜好品としての楽しみは一部の人の限られたものとなって参りました。
本来、茶は茶園毎に異なる性質を持ち、その特徴は多種多様な物です。そして、茶の世界を楽しむ人たちのお茶に対する楽しみ方やこだわりも、それぞれ異なっているはずなのです。私達はお客様お一人お一人の声を茶葉の製造に活かしながら、お客様の求める高い品質の茶葉やすぐれた特徴のある茶葉をご提供したいと考えております。そして、お一人でも多くの人達にお茶のすばらしい世界を実感していただく事が私達の使命であると考えております。
そして、それは茶業者である私達だけの努力のみでは成り立ちません。茶葉の栽培に携わる多くの農家の人達との密接な関係とコミュニケーション、そして品質に対するこだわりやたゆまぬ努力を通じてしか達成できないと考えております。価値観の多様化した現代のお客様の声を茶葉の栽培と製造に活かし、そして最高の形で製品としてお客様のもとへお届けするために、私達はこれからも努力と革新を続けてまいりたいと考えております。
|
|
|
|
|
|
株式会社西出製茶場
代表取締役 西出孝
|
|
|
|
|
|
|
|
| ◆価値観について |
|
|
|
お茶は、生活用品として人々の生活に密接したモノでありながら、一方で長い歴史の変遷を経て発展を遂げてきた、和の心を象徴する文化でもあります。
私達は、茶葉の鑑定・製造においては、茶葉をモノとして見極め、厳しい品質の検査および鑑定を行う一方で、自らの鑑定力の向上・製造方法の改善を通じて品質の向上に尽力しております。
一方で、お茶を求めるお客様に対しては、歴史・文化そして、茶葉栽培や緑茶製造における数多くのこだわりや価値、さらに健康やリラックスをもたらすすばらしいお茶の側面をお伝えし、お茶の持つ物質的な価値をはるかに超えた豊かな文化的な価値をご提供する事が社会に対する大きな貢献であると考えております。
私達は、それらを価値観の基礎として心に刻み、日々の業務の遂行にあたっております。
|
|
|
|
|
|
| ◆わたしたちの目指すところ【企業理念】 |
|
わたくし達、西出製茶場のメンバーは、以下に掲げる理念を常に心に抱き、その理念を達成するために切磋琢磨し、常にプロの業者としてのたえまぬ努力と自らの革新を続けてまいります。 |
|
|
|
|
お茶及びお茶文化の普及を通じて、心豊かな人々の生活と、思いやりに満ちた社会の実現に貢献する事
|
|
|
| ◆宇治茶といえども千差万別 |
|
宇治茶の生産地はここ宇治田原を始め、宇治白川・和束・南山城・田辺・加茂等広範囲に渡り、さらに玉露・煎茶・深蒸し煎茶・かぶせ茶等茶種によっても産地の違いや特徴は全て異なっています。
ふつうお茶屋さんでは、ブレンドによって茶葉の長所を生かし欠点を隠しながら質の整ったお茶を仕上ていきます。もちろんそのような茶作りは大切なことですし、それもおいしいお茶作りの条件ではあります。ただ、それとは別に生産地や生産家の特徴を前面に押し出したストレートなお茶を味わっていただくのもお茶の楽しみの一つなのではないかと考えております。
そのようなことをふまえながら、当店では宇治茶の良さを最大限に引き出し各産地の茶葉の特性を生かした茶作りを常に心がけております。宇治茶の良さ、日本茶の良さを是非知っていただきたい。お茶を入れるのは面倒ですが、その先にはきっとすばらしい発見があるはずです。 |
|
|
|
| ◆あなただけの特別な一杯を是非見つけてください。 |
|
そして、お茶の楽しみ方は千差万別、人それぞれに好みのお茶も違います。当店ではどのようなお茶の好みにも答えられるようきめ細やかな対応を心がけております。お気軽に何でもご相談ください。
そしてあなただけの特別な一杯を見つけてください。 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
| 店長 |
西出 孝(にしで たかし) |
| 所属 |
京都府茶業青年団
宇治田原手揉み保存会
|
|
全国茶審査技術五段位 |
|
|
代々の茶屋に生まれて以来茶に囲まれて毎日を送っています。
先代の茶に対する真剣な姿勢と楽しそうな仕事ぶりにあこがれ、一緒に仕事がしたいなあと思ったのが茶屋への第一歩でした。
今では茶の審査をしない日はなく、品質チェックが日課の毎日です。現在はお茶屋の視点ではなく、お客様の視点や生産農家さんの視点でお茶を見直したいなと考えています。日本茶の世界は深く・広くそしてとっても楽しいということが皆様にわかっていただければと常々考えています。 |
|
|
|
|
|
|
| 店舗スタッフ |
西出 淳子(にしで あつこ) |
|
日本茶インストラクター |
|
本当はお茶は素人でしたが、いつの間にやら日本茶アドバイザー・日本茶インストラクターを続けて取得し、今ではお茶についての一般常識についてはある程度説明できるようになりました。
お茶のおいしい入れ方など、ご質問は遠慮なくこちらまで。
E−mailでのご質問だと適切にお返しできるかと思いますのでそちらをご利用ください。 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
| ◆茶栽培へのこだわり |
|
茶は同じ畑であっても毎年出来が異なります。気象条件・摘採時期・肥料の与え方など、1年を通して茶葉の生育に目を配ることが大切だといえます。わたしたちは生産農家の人たちとの交流や意見交換・もしくは生産履歴のチェックなどを通じて、より良いお茶作りを目指して行きます。 |
|
|
|
|
|
| ※左は宇治田原の煎茶用茶園・右は玉露用茶園を撮影したものです。玉露には太陽の光を遮る覆いがかけられます。 |
|
| ◆茶葉そのものへのこだわり |
|
お茶は、摘みとられてた後すぐに製茶工場に運ばれ、『荒茶』と呼ばれる半製品になります。この荒茶こそがそのお茶の良し悪しを決める全ての基本となります。
お茶は茶畑での生葉の状態だけではまだ良い茶になるかどうかわかりません。生葉を蒸し、揉み上げてこそ初めてその茶の姿が見えてくるといえます。
私たちはこの荒茶を見定めることで、本当の良いお茶を見つけ出し、その特徴を生かした茶作りを極めるために日々努力を重ねています。
|
|
|
|
|
| ※仕上の済んだ茶葉や荒茶は専用の道具で常に出来を審査します。熱湯でお茶を出すことで香りや味のくせが引き立ちます。また水の色や濁り、茶殻の色なども審査の基準になります。 |
|
| ◆茶葉の秘めた力へのこだわり |
| 荒茶となったお茶は精選加工の工程を経て、商品としてのお茶へと姿を変えていきます。荒茶を生かす、生かさないはこの精選で決まります。いかに迅速に、又いかに最適な加工がなされるかが勝負といえます。ここでは経験と技術が必要とされます。 |
|
|
|
| ※仕上げ加工(葉揃え)と乾燥火入(小型棚乾燥)の様子。比較的上級品になると上のように少量で仕上がり具合を見ながらの加工作業となります。仕上げ途中で茶葉の様子から加工の方針が変更になることもしばしば。 |
|
| ◆鮮度・品質管理へのこだわり |
|
茶葉にとって温度・湿度の管理は本当に大切なものといえます。私たち業者にとって茶葉専門の冷蔵庫による保管は基本条件です。
茶によっては長期間保管をすることによってあくが抜け、熟味が増す場合がありますが、そのような場合でも適温適湿であるということが必要条件であって、ただ時間だけが経過したお茶は単に痛んだお茶となるだけなのです。どんなに良いお茶であっても保管の良くない茶は品質が極端にさがります。
出来上がった最高の姿でお客様のもとへ届ける、ということ。これが大切なのです。
|
|
|
|
|
|
| ※当店のお茶は緑茶専門の冷蔵庫にて常に低温保管されております。 |
|
| ◆茶作りのプロであるということ。手作りであること。 |
|
機械を用いないというわけではないのですが、本来お茶は茶葉一葉一葉が違うものであるということを常に心におきながら、茶そのものの持つ生まれながらの特徴を生かし、最大限にお茶のおいしさ、すばらしさを引き出す努力をおこたりません。私たちはお茶作りのプロとして自身の感覚を研ぎ澄まし、最高のお茶づくりに励んでまいります. |
|
|
|
|
|
|
|
 |